トゥットゥルー♪
こにゃにゃちはレオナルドです!
本記事はこんな方にオススメ
- アウトプットお化け精神科医・樺沢紫苑さん著「読んだら忘れない読書術」の内容・要約が知りたい方
- 読書で効率的に自己成長したい方
- 悩みを解決したい方
- 読書の時間がない方
この記事によって分かること
- 「読んだら忘れない読書術」の内容
- 読書で効率的に自己成長する方法
- 悩みの解決方法
- 忙しくても本が読めるようになる
ざっくり結論
先にレオナルド的ザックリ結論を書くと
「読書は人生で大切なものすべてを与えてくれる。効率的に読書して、先人たちの知識・経験を吸収し、自己成長して、人生を豊かにしよう!」
といったところでしょうか?
文化庁の調査によるとなんと日本人の半分は本を全く読まず、
月7冊読むだけで読書量が日本人の上位4%に入ってしまうとのこと。少ないと思っていたけど、これほどまでにみんな読書しないとは。。
なぜ多くの人は本を読まないのでしょうか?
意味を感じない、時間がない、楽しくない、様々な理由があると思いますが、結果が出ない=意味がない、だから楽しくないからそんなことに割く時間はない、といった思考かなと思います。
本書では冒頭で、読書は「健康」「お金」「時間」「人(つながり)」「自己成長・自己実現」すべてを与えてくれると語られています。本を読まない人はこのメリットを知らないだけで、どうすればこのメリットを見出すことができるか本書で解説されているので見ていきましょう。
なぜ読書は必要なのか読書によって得られること8つ
結晶化された知識
1年たって古くなるのが「情報」、古くならないのが「知識」です。
ネット、テレビ、新聞、雑誌、週刊誌、ネットニュース等で得られる内容の大部分は「情報」で、体系的だった本から得られるのが「知識」だとのこと。
「単なる知識」ではなく「結晶化された知識」。単なる羅列された文字情報ではなく、実践可能、応用可能で行動に繋がり、10年たっても風化することのない「結晶化された知識」を得られるのが「本」だと語られています。
「本」では、既に、著者が情報を分析し、整理し、体系化してくれているので最初から「知識」が書かれています。「本」から直接「知識」を吸収するほうが、一から学ぶよりも100倍楽であり、効率的です。
確かに、私もネットで情報ばかりを見ているような気がします。
それよりも既に結晶化された知識を本から得る方が効率的ということですね。
もちろん、情報も大切ですが、必要な情報を得ながらも、自分で様々な内容の本を読み、「情報」と「知識」のバランスをとっていくことが大事とのことです。
時間
本には、何千人もの成功体験と、何千人もの失敗体験が載っています。ありとあらゆる成功事例と失敗事例の集大成が本といえます。
何か新しいことを始める場合、完全にゼロからスタートするのと、「1000人の成功体験と1000人の失敗体験」を本で学んでからスタートするのとでは、どちらが有利でしょうか?
もちろん他人の体験がそのまま全て自分に当てはまるとは限りませんが、他人の経験を参考にすることで、自分でゼロから行う無駄な試行錯誤を省略できます。
鉄血宰相と呼ばれたビスマルクの「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」という有名な言葉がありますが、まさに本を読んで他人の経験やこれまでの歴史を吸収し様々な部分で時間短縮して圧倒的な結果を生み出すといった内容に置き換えることができると思います。
人間に平等に与えられている時間を他人より多く得ることは最も大きい恩恵だと私は思います。
他の6つはさらっと要約しますが、もっと知りたい方は是非本書を手に取ってみてください。
仕事力
ライバルに圧倒的に差をつける第一歩が、読書量を増やすことである。
健康
ある研究で、読書、音楽視聴、コーヒー、ゲーム、散歩の中で、読書が最も高いストレス解消効果が得られた。6分間の読書で、ストレスを2/3以上軽減できるとのこと。
頭が良くなる
読書は「物知り」にさせるだけでなく、「地頭が良くなる」「知能が高くなる」「脳が活性化し、脳のパフォーマンスが高まる」と、多くの脳科学研究が示している。
人生における変化
自分の頭でいくら状況を打開する方法を考えても、限界がある。しかし、「本」を読めば先人の知恵を借用でき将来の選択肢が広がる。
成長
読書によって「考え方」だけでなく、実際に自分の「行動」を変化させることで、自分を取り巻く現実が良くなり、確実に自己成長する。
喜び
楽しみながら読むだけで、記憶にも残り、学びも大きく、自己成長に繋がる。「自己成長」を目的としないほうが、結果として猛烈な自己成長に繋がる。
読んだら忘れない読書術3つの基本
アウトプットすること~「記憶に残る読書術」
本を読んだけど何も覚えていない。そんな時ってありませんか?
本を読んで得た知識を定着させるためにはアウトプットをすることが重要で、本を読む=インプットするだけではなく、アウトプットを対で行うことで本を読んで得た知識が、自分の血肉となると語られています。
アウトプットについて詳細に知りたい方は、
樺沢先生のアウトプットについての集大成「アウトプット大全」についての別記事がありますので、詳しく知りたい方は是非参考にしてください。
効率的に読書する~「スキマ時間読書術」
筆者の樺沢さんはスキマ時間で月30冊の本を読むとのこと。そして驚くことが別に速読しているわけではないということです。
例えば、東京で通勤するサラリーマンの通勤時間の平均は往復で2時間だそうで、休日もスキマ時間があるとして、合計すれば月で60時間になります。この時間を使えば、本を読むのが遅くても10冊は読めるはずとのこと。
確かに。。。。。
その中で、多くの人は電車で何をしているのでしょうか?
スマホを触ってゲームをしているか、よくても「知識」ではなく「情報」を集めている人がほとんどではないでしょうか?
その行為は時間の無駄とハッキリとおっしゃられております。。。。。
すいません。。。そのとおりです。。。。(´;ω;`)
ってなっちゃいますね。。。
2時間は1日の1割です。
人生の1割に相当するスキマ時間を「浪費」に使うのか「自己投資」に使うのか。この時間の使い方で人生が変わるということですね。
「速読」より「深読」を意識する~「深読読書術」
「本を読んだ」の定義は、「内容を説明できること」「内容について議論できること」。「深読」は読書の必要条件であり、「深読」できるようになってから、「速読」「多読」を目指すべきで内容を覚えていなければ、速読しても意味はないとのこと。
究極の電子書籍術
書籍は、電子か紙かという議論があると思いますが、樺沢さんは使い方次第で、ともにメリットがあるとおっしゃっています。
ここではメリットを8つ記載します。
- 持ち運びが楽
- 本の保管が簡単
- 紙の本よりも安くて読書量が増える
- 購入した直後から読め、時間短縮になる
- いつでも好きな時に読み返せる
- 秀逸すぎる「ハイライト」機能で復習が楽にできる
- 満員電車の中で読みやすい
- 老眼にやさしい
私も電子書籍チャレンジしてみよー!
まとめ
単に本を読むにしても、「どう読むか」がいかに重要か教えてもらえました。
「アウトプット」「スキマ時間」「深読」この3つを意識して読書していきたいですね!
そして、本で得た知識をもとに「行動の変化」を起こし、「自己成長」へとつなげていきたいですね!このブログもアウトプットのつもりですwww
本書の最後に、筆者のおすすめする31冊の本が紹介されています。
それも含め、もっと詳しく知りたい方は、是非本書で理解を深めてみてください。「本」を読むための「本」として間違いない1冊になるはずです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます(^^)
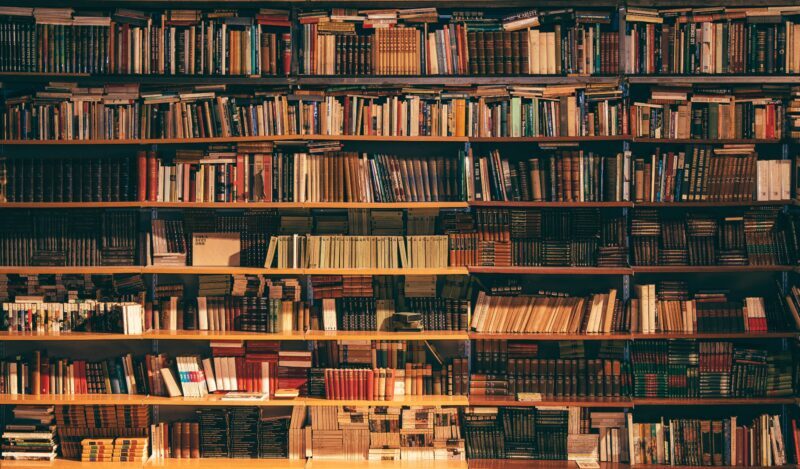



コメント