レオナルドです!
今回も前回の続きで、超有名書籍ジャレド・ダイアモンド(Jared Diamond)氏の世界的ベストセラー「銃・病原菌・鉄」についてです!
前回の記事がまだの方はぜひ!!!↓
他の書籍要約記事とは違い、自身の備忘録的な感じになりますが、良ければ最後まで読んで頂けますと嬉しいです。
第2部 食料生産にまつわる謎(食料生産と征服戦争;持てるものと持たざるものの歴史;農耕を始めた人と始めなかった人;毒のないアーモンドのつくり方 ほか)
4章 食糧生産と征服戦争
狩猟採集ではなく農耕家畜が発達したら?⇒定住になる⇒人口稠密⇒食料余剰⇒非生産の人が生まれる⇒政治が発達複雑⇒帝国発足
家畜が発達⇒動物の病原菌が人への病原菌に変異⇒病原菌の免疫ができる⇒免疫を獲得するには遺伝も含め時間がかかる⇒免疫がない人類が病原菌に増えるとその人類は壊滅する。
ということは、早い段階で農耕家畜が発達した地域が有利
5章 もてるものと持たざるものの歴史
食料生産が最初に始まったのは
メソポタミアの肥沃三日月地帯(東南アジア)
中国
中米
南米のアンデス地帯
合衆国東部
の5地域とされていて、その最古はメソポタミアの紀元前8500年頃である。
メソポタミアで始まった農耕が、ヨーロッパ・エジプト・インダス川流域に伝播していったが、何故、紀元前8500年頃の、しかもメソポタミアが最初だったのであろうか?
実際、肥沃な土地でも農耕を採用せず、狩猟採集してたとこも多い。
いち早く農耕家畜を始めたこのちょっとした差が、先に病原菌に対しての免疫を獲得できたりといった差になっている。
6章 農耕を始めた人と始めなかった人
人類の集団が、狩猟採集から食糧生産型への移行を決断するには様々な条件があり、急に変わるものではない。
なぜなら、毎日目の前にその日必要な食糧や獲物がいるなら、まだ農耕が確立されていない段階で、未来の不確実な食糧のために労働するという動機が発生しないから。
狩猟採集から食糧生産型への移行への大きな要因は5つある。
①狩猟可能な野生の哺乳類が減少による、狩猟の生産性の低下
②栽培可能な野生の穀類が増加
③野生の穀類を効果的に収集、加工、貯蔵する技術が発明された
④人口密度が高まり、食料を生産する必要に駆られた
⑤農耕民の人口が増え、狩猟民族を追い払うようになる
7章 毒のないアーモンドの作り方
農耕を始めた人類は、野生種の中から「実が大きい」「油分が多い」「繊維組織が長い」といった基準で個体を選定し、栽培種へと変化させていった。若しくは、突然変異によって、より栽培しやすくなった個体(自家受粉可能な個体など)を採用した。
例えば小麦の野生種は、穂先の実を自ら撒き散らして生存の確立を高める。しかし、人類は、人類にとって都合の良い実を巻き散らかさず、同じタイミングで発芽する遺伝子変異を起こした小麦を栽培し、栽培種へと移行させた。いわば「人為的な」自然淘汰である。
このように、自然淘汰のベクトルを人間が反転させてしまった状態である。
動物・植物ともに劣勢であっても人間に都合のいいものを無意識に採集して排泄等でばらまいたため、そういった種が生き残っている。
8章 リンゴのせいか、インディアンのせいか
栽培化とその発展を決めるものは、「入手可能な動植物の差」と「狩猟採取生活から農耕生活に移行するインセンティブ」である。
その中で、
メソポタミアは「地中海性気候」「一定の面積」「変化に富む地形」により、他の地域より植物が多様で、栽培種に移行しやすい野生種や自殖性植物(雌雄同体の自家受粉植物=突然変異を容易に子孫に伝達可能)が多かった。
家畜化可能な哺乳類も多くの種類生息しており、その動物を食糧にだけでなく衣類・労力・輸送力として活用することで、農耕牧畜への移行をスムーズにした。
よって、メソポタミアとその他地域の違いは、入手可能であった野生動植物の差であり、人々の能力や文化的価値観の差ではないと考えられる。
9章 なぜシマウマは家畜にならなかったのか
20世紀までに家畜化された種は14種しかなく、その多くが世界の大陸の中で最も面積が広く、そのぶん生態系も多様だったユーラシア大陸に存在した。
また、家畜化できる動物の条件は6つある。
①餌について
人類が妥当な労働の中で提供可能な餌でないといけない。
肉食動物はもちろん、ものすごく大量に餌を必要とする草食動物の家畜化できない。
また、コアラのように偏食でもNG。
なので、普段家畜化されていない動物の肉を食べることはあまりないと思うがライオンバーガーうまいらしいwww
②成長速度の問題
これは栽培種にする植物にも当てはまることだが、成長が遅いと家畜化する意味がない。
ゴリラとかゾウがそれにあたる。
③繁殖上の問題
衆人監視化のセックスを好まない動物も多い。
そういった動物は家畜された状況で子孫を残さないので家畜化できない。
チーターとかビクーニャがこれにあたる。
厳密には衆人監視化では、交尾の前の求愛行動ができない。
④気性の問題
気性の荒い動物は家畜化できない。
クマの肉は珍味だし草食だが気性が荒く家畜化できない。
アフリカ水牛、カバもこれにあたり、シマウマもこれにあたる。
因みに人間を年間で一番多く殺しているのはカバである。(ヒトという動物を除けばwww)
⑤パニックになりやすい性格の問題
ガゼルのようなパニックになりやすい性格の動物は家畜化できない。
⑥序列性のある集団を形成しない問題
序列の習性がない1匹を好むタイプは集団で飼育できないので家畜化できない。
そして、群れを作る動物ならOKかというとそうでもない。
群れ同士で争われては困るし、繁殖期に縄張り意識が強くなられても困る。
10章 大地の広がる方向と住民の運命
ユーラシア大陸は同緯度帯で東西方向に広がっているため、南北に広がる南北アメリカ大陸やアフリカ大陸に比べて、大陸内で似たような気候や生態系になっている。
食糧栽培の農耕技術は環境が類似している状態でしか横展開できないので、南北アメリカ大陸やアフリカ大陸に比べて、ユーラシア大陸では栽培化や家畜化に適した動植物の伝播が速かった。
実際、肥沃な三日月地帯を起源とする農作物には、単一栽培種を祖先とする作物が多い。
これは、周囲の地域で確立できた農耕技術を真似すればいいだけなので、その他の現地種の栽培方法を模索する必要がなかったと考えられる。
一方、南米アメリカ大陸やアフリカ大陸では、各地の現地種が栽培品種化されることが多かった。
次回…第3部_銃・病原菌・鉄の謎 & 第4部_世界に横たわる謎
第3部:銃・病原菌・鉄の謎(家畜がくれた死の贈り物)&第4部:世界に横たわる謎の記事↓
#歴史#考古学#人類史#人類学
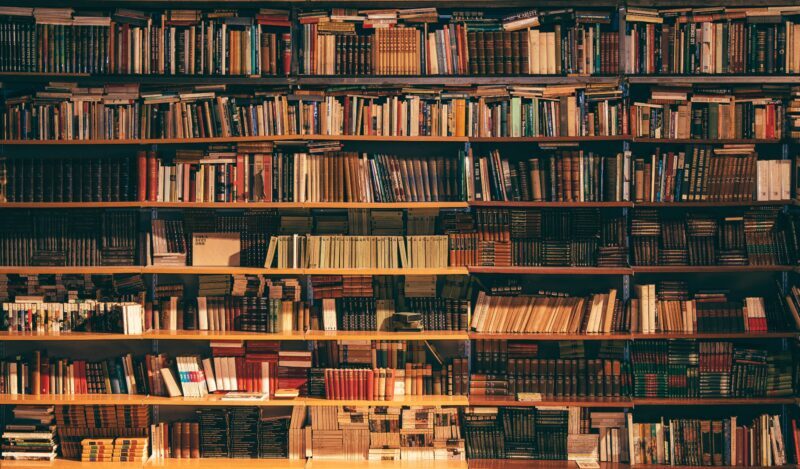



コメント